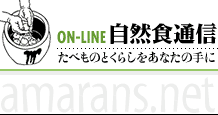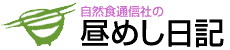・ 間引き人参炊き込みごはん
・ 味噌汁(筍・ジャガイモ・菜花)
・ おぼろ豆腐・人参・大根・コンニャクの炒め煮
・ サニーレタスと卵白・チリメンジャコのサラダ
間引き人参、もう一度くるかなあ
初々しい間引き人参を食す日々も、とうとうこの炊き込みごはんにて終了です。人参本体も葉も、色は淡く、香りもやさしいから生で使ったり、火も通しすぎないようにね。
塩をほんの少々入れてごはんを炊き、電気釜のスイッチが切れる寸前に粗いササガキに切った人参をごはんの上に載せて軽く蒸らします。よそう際にみじん切りにした葉をたっぷり混ぜ込んで。う~ん、薄緑色の葉の香りが食欲をそそりますぅ~。
 “おぼろ豆腐”は、日持ち抜群の凍み豆腐をぬるま湯に浸したのをぎゅっと絞っておろし金(穴あきタイプね)でざざっとおろしたもの。これがちょうどいいおろし加減なのです。短冊に刻んだ人参・大根・コンニャク(はさっとゆがくと凝固剤のアルカリ分がいくらかぬけます)を少量(野菜が焦げつかないていどの)だし汁・砂糖・酒・塩・薄口醤油で蒸し煮に。
“おぼろ豆腐”は、日持ち抜群の凍み豆腐をぬるま湯に浸したのをぎゅっと絞っておろし金(穴あきタイプね)でざざっとおろしたもの。これがちょうどいいおろし加減なのです。短冊に刻んだ人参・大根・コンニャク(はさっとゆがくと凝固剤のアルカリ分がいくらかぬけます)を少量(野菜が焦げつかないていどの)だし汁・砂糖・酒・塩・薄口醤油で蒸し煮に。
野菜から意外なほど水分が出てくるので、そこにおろした凍み豆腐を加え、全体に味がしみ込むよう煮詰めれば出来上がり。
 先週金曜に卵黄を使った残りの卵白が2個分冷蔵庫にあるのを発見。土日が入るとしっかり忘却の彼方。何とか使わなくては。というわけで、油を熱し、チリメンジャコを炒めたところに溶いた卵白を加えてス、クランブルエッグに。
先週金曜に卵黄を使った残りの卵白が2個分冷蔵庫にあるのを発見。土日が入るとしっかり忘却の彼方。何とか使わなくては。というわけで、油を熱し、チリメンジャコを炒めたところに溶いた卵白を加えてス、クランブルエッグに。
サニーレタスも1把分あるじゃないですか。すぐに嵩を減らそうと頭の中は目まぐるしい。お湯を沸かし、洗ってほぐしたレタスをさっとくぐらせ、ざるにとれば余熱で傘は5分の1ほどに。しめしめ。
水気を絞って、ざくざくときざんで皿に敷きつめ、白身スクランブルエッグをトッピングに。けっこうボリュームあるように見えますね。バルサミコ酢+醤油、オリーブ油を回しかけて。
 筍も初物。まだえぐみも少なく、アク抜きをしなくてもよかったかな。家から持参です。
筍も初物。まだえぐみも少なく、アク抜きをしなくてもよかったかな。家から持参です。
実家では、筍を味噌汁に入れるのがまず最初でした。アク抜きもせず、いちばん軟らかいところを薄く刻んで、蕪のつまみ菜を合わせるのが定番。この時期、八百屋の店先にはおおきな籠につまみ菜が山盛りになっていました。今もあちらでは蕪が大きくなっていく節目節目で間引きした「蕪菜」を使っているのだろうか。
きょうはジャガイモをお伴に。椀によそうときにさっと湯をくぐらせた菜花をのせれば、料亭もかなわぬ最強の味噌汁に。シアワセな昼飯じゃった。